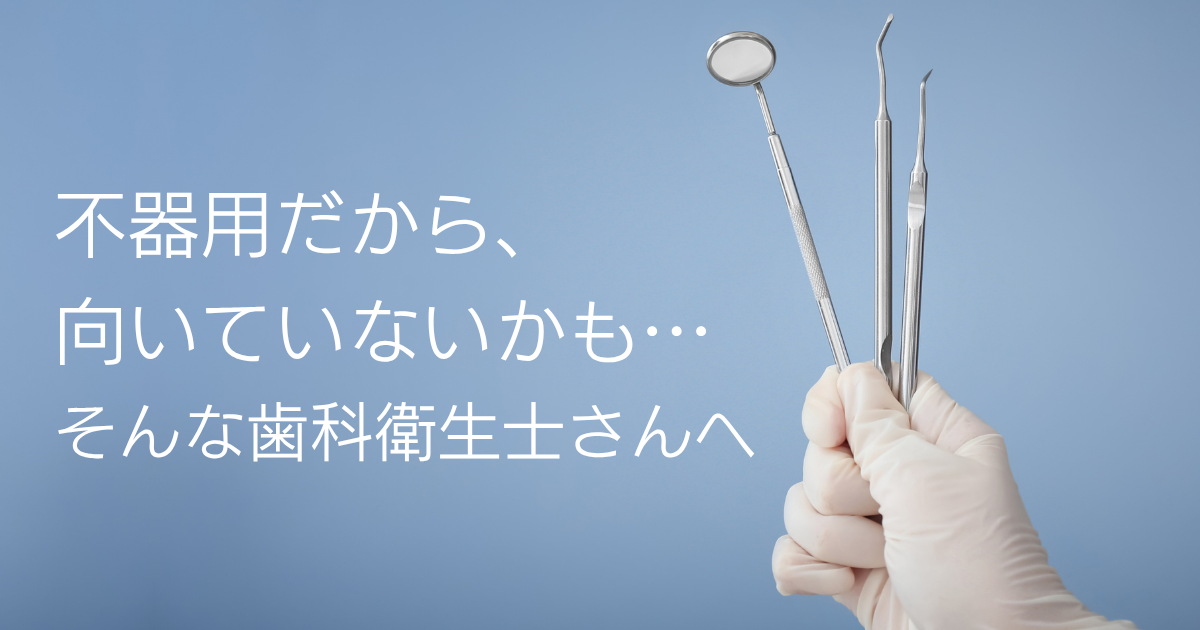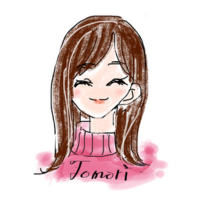「このままいくと今日のSRP、予定通り終わらないかも…次の予約、いつだっけ?先生の治療との兼ね合い、大丈夫かな?…っていうか、さっきの歯石どこいった?!」
これは、初めて患者さんを担当するようになってから半年くらいの頃の、私の心の声です。
「先生に聞いてみようかな?でももう時間がない…。先輩たちみたいに歯石を綺麗に早くとれないし…私ってほんと不器用だな…」
そんな考えで頭がぐるぐるして、手元は焦ってうまく動かないし、器具が滑って患者さんの表情が曇っていく……。そのときのドキドキと、胸がギュッとなる感覚、今でもはっきり覚えています。
でも今なら、あのときの私にこう声をかけたい。
「そんなに思い詰めなくていいよ。大丈夫、ちゃんとできるようになるから」
大切なのは、“できなかった自分”を責めることじゃなくて、
“できるようになりたい自分”を、認めて、信じてあげること。
「不器用=手先がうまく動かないこと」って思われがちですが、実は、「できない自分に落ち込んでしまう」「周りと比べてつらくなる」、そんな『心の不器用さ』に悩まされている人も、少なくありません。
この記事では、そうしたメンタル面と技術面、両方の側面から『不器用でできない』を整理して、『できるようになる』ヒントをお話ししたいと思います。
もし今、「私って不器用かも…」「向いてないのかな」と感じている方がいたら、少しでも心がふっと軽くなるヒントを届けられたら嬉しいです。
「不器用でダメだ」という気持ちを整理する
「私って不器用だな…」って感じる瞬間って、どんな時でしょうか。
- SRPでどうやっても歯石がうまく取れないとき
- 器具の使い方がうまくいかず患者さんに痛みを与えてしまったとき
- 細かな作業で手元が狂ってしまったとき
- 時間内に処置を終えられなかったとき
特に、他のスタッフがサクサク進んでいく中で、なぜか自分だけがもたついて遅れをとってしまったら…「私って不器用でダメだな」と感じてしまいますよね。その上先生に指摘されたり、「なんでできないんだ!」なんて怒られたりしたら、たまりません。
でも、それって本当に“不器用だから”なんでしょうか?
まずは「不器用でできない」と思うのはなぜか、整理してみましょう。
「心の不器用さ」と「技術的な不器用さ」
うまくいかなかった理由を、「私って不器用」のひと言で片づけてしまうのは、少しもったいない気がします。というのも、こうした状態の「不器用さ」は、手先の技術の問題だけでなく、“心の不器用さ”が大きく関わっているからです。
心の不器用さとはつまり、「できない自分をどう受け止めるか」や「周りとの比べ方」による心の揺らぎ。
私自身、そういった心の部分にはかなり悩みました。
私の場合、誰かに怒られたわけではないけれど、先生や患者さんの残念そうな顔や、ちょっと張りつめた空気を感じた瞬間に、「できなかった自分」を強く責めてしまっていました。
「次はうまくやれば大丈夫だよ!」と声をかけてもらっても気持ちがついていかなくて、「不器用なのかな」と自信をなくし、その気持ちを引きずったまま次の処置に向かうと、やっぱり手元がうまく動かない。「次こそはなんとかしなきゃ!」と思っても、焦りばかりが先に立って空回り…やっぱり失敗して、また自信をなくしていく…という負のスパイラル。
「できない自分」を責めて落ち込む
↓
自信がなくなる
↓
焦ってさらに手元が不安定に…
この悪循環を止めるためにまず必要なのは、「不器用だ」と感じた時に、その「不器用さ」がどこから来ているのかを整理してみること。
もしかしたら、根本にあるのは「心の不器用さ」かもしれません。私も最初は「不器用だからできない」と思っていたけれど、実は「できない自分を責める気持ち」が「私は不器用なんだという思い」を強めていたのかもしれない、と今なら思います。
技術的な問題と心の問題、それぞれを分けて考えてみることで、少しずつ解決策が見えてきます。
自分の悩みの根源を明確にしてみよう
まずは、自分がどこでつまずいているのか、何に不安を感じているのかを「言葉にして整理」してみましょう。
- つまずきを感じたことを振り返る
- 原因を探る
- 「技術的な問題」と「心の問題」に分けてみる
実際にひとつ、例を見ながら一緒に考えてみましょう。たとえば、「SRPがうまくできない」という悩み。
STEP1:つまずきを感じたことを振り返る
「SRPがうまくできない」をもっと具体的に、どんな場面で「できなかった」と感じたのかを振り返ります。感じたこと、起きたことをなるべく細分化して、紙に書き出してみましょう。
- SRPがうまく進まず時間内に終わらなかった
- 歯肉縁下の歯石がどうしても見つけられなかった
- スケーラーの刃の角度がうまくつけられず空振りしてしまった
- 操作に自信がなくて手が震えてしまった
- 患者さんの反応が気になって力加減がわからなくなった
STEP2:原因を探る
こんな風に感じたのは、それぞれ何が原因だったのでしょうか?ひとつひとつ、掘り下げてみましょう。
-
SRPがうまく進まず時間内に終わらなかった
- 「時間内に終わらせなきゃ」という焦りが強く、ひとつひとつの処置に余裕がなくなっていた
- 前の患者さんが押していて、始まりから気持ちが落ち着かなかった
- 歯石の位置がよくわからず何度も同じ場所を探ってしまった
- ミラーの操作に気を取られてスケーラーの先がどこを触っているのか感覚がつかめなかった
- 処置の見通し(どこにどれくらい時間がかかるか)がよく掴めていない
- アシストに気を遣いすぎて自分の動きに集中できなかった
- 歯肉縁下の歯石がどうしても見つけられなかった
歯石の「感触」がまだ自分の中で明確になっておらず、どの感触が“当たり”なのか分からないまま探り続けていた。プロービングの精度や触診の練習量が足りていないのかもしれない。
- スケーラーの刃の角度がうまくつけられず、空振りしてしまった
正しい挿入角や作業角度の「イメージ」がまだ曖昧。頭では分かっているけど、手元で再現する練習が足りていないのかも。
- 操作に自信がなくて手が震えてしまった
「失敗したらどうしよう」「間違えちゃいけない」という不安が強く、気持ちが体に緊張として表れた。もしかすると、“見られている”ことへの緊張感も影響していたのかも。
-
患者さんの反応が気になって力加減がわからなくなった
「痛がらせてしまったらどうしよう」という気持ちから、自分の手の感覚よりも患者さんの表情ばかりに気を取られすぎていた。その結果、どれくらいの力でやるべきか分からなくなってしまった。
STEP3:「技術的な問題」と「心の問題」に分けてみる
できなかった原因を見て、技術的な問題と心の問題を分けてみましょう。
- 歯石の位置がよくわからず何度も同じ場所を探ってしまった→触診の感覚や歯石の付着パターンの理解がまだ不十分
- ミラーの操作に気を取られてスケーラーの先がどこを触っているのか感覚がつかめなかった→鏡視下での操作にまだ慣れていない/器用さの問題というより、慣れと練習の量が影響
- 歯肉縁下の歯石がどうしても見つけられなかった→縁下の触知スキルや、プロービングの活用、器具のコントロールの問題
- スケーラーの刃の角度がうまくつけられず、空振りしてしまった→挿入角・作業角の理解や、保持の安定性などの基本操作の技術課題
- 患者さんの反応が気になって力加減がわからなくなった→力加減の基準が自分の中で定まっていない
- 「時間内に終わらせなきゃ」という焦りが強く、ひとつひとつの処置に余裕がなくなっていた→焦りやプレッシャーによる緊張、自己への期待や不安
- 前の患者さんが押していて始まりから気持ちが落ち着かなかった→時間に追われて余裕がなくなる/気持ちの切り替えが難しい
- アシストに気を遣いすぎて自分の動きに集中できなかった→相手への気配りで自分のペースが崩れてしまう/遠慮しすぎる
- 操作に自信がなくて手が震えてしまった→「失敗したらどうしよう」という不安・自信のなさからくる身体反応
- 患者さんの反応が気になって力加減がわからなくなった→相手の反応に敏感になりすぎて自分の感覚を信じられなかった
最後に、整理した内容を見比べてみましょう。技術的な問題と心の問題、どちらの方が多いですか?自分がはじめに思っていたこととは違うことが浮かんできましたか?技術的に足りない部分があったとしても、心の問題(焦りや不安)が原因でうまくできなかった場合もあります。
「不器用だからできない」、ではなくて、こんなふうに「どんなことを不器用と感じたのか」「何ができなかったのか」、自分の悩みの根源を明確にすることで、「何をすべきか」が見えてきますし、少しずつ改善していくヒントがつかめるはずです!
心の不器用さの問題に向き合う
心の不器用さというのは、なかなか簡単には改善しづらい部分。だからこそ、「できない自分」を感じやすく、さらに不器用さを悪化させてしまうこともあります。「心の不器用さと向き合う」ということは、『不器用でできない』を脱却するための大事なポイントです。
事実と思い込みを分けるワークをやってみよう
「自分はできない」「向いてない」と感じるとき、頭の中はモヤモヤでいっぱいになります。そんな時は、紙に書き出してみるワークがおすすめです。
まずは思っていることを、そのまま素直に書き出してみましょう。
-
「どうせ私には無理」
-
「またできなかった」
-
「先輩みたいにはなれない」
-
「私って本当に不器用」
とにかく思いつくままに書いてOK。正しさより「今の気持ち」を出すことが大切です。
ステップ①で書き出した内容を「思い込み」「事実」「感情」に分類してみて、なぜそう思ったかを書き出します。
| 内容 | どの分類? | なぜそう思った? |
|---|---|---|
| 私には無理だ | 思い込み | 一回の失敗で自信をなくしていた |
| スケーリングで患者さんが痛がった | 事実 | 実際に患者さんが反応した |
| 先輩に比べて私はダメだ | 感情 | 比べてしまって落ち込んでいる |
正しく分けることが目的ではないので「これかな?」と曖昧でもOKです。「なぜそう思ったか?」 を書いてみると、自分の中にある「評価の基準」や「不安の種」も見えてきます。
-
「私には無理だ」→「苦手なこともあるけど、得意なこともある」
-
「またできなかった」→「何がうまくいかなかったのか、考えて次に活かそう!」
- 「先輩みたいにはなれない」→「やっぱり先輩はすごいな、見習おう!」
この“言い換え”が、心の不器用さをほぐす第一歩になります。
なのですが…正直に言うと、私はこの「前向きな言葉に言い換えてみよう!」というのがちょっと苦手…。落ち込んでるときに、「そんなふうに思わなくていいよ」「もっと前向きに考えたらいいじゃん」って言われると、「いや、そう簡単に切り替えられたら苦労しないよ…」って、逆にしんどくなったこともありました。
私の経験から言えることとしては、そんな時は無理やりポジティブにならなくてもいいということ。「私は不器用」と感じるのなら、そう感じている“自分の本音”をまずはちゃんと見てあげる。そして、ちょっとだけ言葉を“やわらかくしてみる”ことから始めると、少し心がほぐれてくると感じます。
-
「私は不器用だ」→「まだ慣れていないし、苦手に感じてることがある」
-
「私はダメだ」→「今日はダメだったけど、毎回そうとは限らない」
-
「またできなかった」→「今日のやり方ではうまくいかなかっただけかも」
こんな風にちょっと付け足したり、やわらかく言い換えてみるのがおすすめです。このやわらかい言い換えは、前向きになるためじゃなくて、「今の自分を否定しないため」の言葉です。
うまく言い換えられない日があっても大丈夫。「そんな日もあるよね」と自分に言ってあげるだけでも、心の不器用さは少しずつほどけて、結果、気持ちが前に向いて行くと思いますよ。
うまくいかなかったことの裏には、「実はできていたこと」もあるはず。これはできていた!と思うことを探して書き出してみましょう。
-
手順は間違えていなかった
-
声かけは丁寧にできていた
-
痛みのある箇所に気づいて配慮しようとしていた
小さなことでもOK。「できなかったこと」と「できていたこと」をセットで見ると、心のバランスが整いやすくなります。
こんなふうに段階を踏んで感情と事実を整理していくと、「不器用かも」「向いてないかも」と感じる気持ちも、“今はそう感じているだけなんだ”って、少しやわらかく受け止められるかもしれません。そう思えたとき、きっとこの先の自分には、まだたくさんの「なれる姿」があることにも気づけるはずです。
技術的な不器用さの問題に向き合う
次に、技術的な「不器用さ」について、少し整理してみましょう。「歯科衛生士は手先が器用じゃないとできない」と言われることがあります。たしかに、歯科衛生士の仕事には、器用さが求められる場面がたくさんありますよね。
-
SRPやスケーリングなどの処置で、細かな歯石を見つけて確実に除去する
-
ミラーやスケーラー、超音波などの器具を適切に使い分ける
-
狭くて見えにくい口腔内で、視野を確保しながら効率よく動かす
-
患者さんに負担をかけないよう、優しい力加減で処置を進める
-
型取りや仮封などの処置で、きれいに整える
-
限られた時間の中で処置をスムーズに終える
こうして見ると、歯科衛生士の仕事はまさに「繊細な操作」と「手際のよさ」が毎日のように求められる、職人のような世界だと言えます。だからこそ、「不器用な私は向いてないかも」と不安になることもあるでしょう。
でも、本当にそうでしょうか?一緒に見ていきましょう。
「不器用だから向いていない」ではなく「慣れていないだけ」
繊細さが求められる歯科衛生士の仕事、これらすべてを初めから完璧にこなせる人なんて、まずいません。
私自身も、最初は「思った通りに手が動かない…」と感じることがよくありました。例えば、上顎臼歯部のSRPの時や、ミラーリングしながら器具操作するとき。頭の中で思う理想の動きとは全然違う手の動きになってしまい、「不器用なのかな?」と落ち込むこともよくありました。
でも振り返ってみると、それは単に「慣れていない」だけだったのかもしれないと思うんです。実際、何度も悔しい思いをしながらも繰り返しやっていくうちに、少しずつ自分の手の感覚がつかめるようになってきたんです。
もともとの器用さよりも、重要なのはやってみるかどうか。そして、慣れていく過程のほうがずっと大切だということ。
たとえ最初はうまくできなくても、何度もやってみて「こうすればいいんだ!」と感覚がつかめたり、繰り返すうちにだんだん手が慣れてきたり。忘れたらまたやり直して、それを繰り返すうちに、ちゃんと手が覚えてくれるようになります。
以前、学生指導に携わっていたので、実習指導でたくさんの学生さんの姿をみてきましたが、最初から完璧にできる人は誰一人いませんでした。「センスがあるな」と感じる人はいましたが、それでも最初は歯石が全部取りきれなかったり、器具が滑ってうまく操作できなかったり、セメントをうまく練れなかったり、石膏をこぼしていたり…。でもみんな、何度もやっていくうちに、だんだんスムーズにできるようになっていく。そんな姿を目の当たりにしました。
だから、「不器用だから向いていない」のではなくて、「まだ慣れていないだけ」。うまくできるようになるスピードは、人それぞれです。練習を重ねるなかで、「できる感覚」はちゃんと手に宿ってきます。安心して、まずは手を動かしてみましょう!
「できるようになる感覚」を掴むために、今日からできること
技術を習得するためには、焦らず一歩ずつ進んでいくことがとても大切です。感覚を掴むには時間がかかるかもしれませんが、急がず、自分のペースで進むことで、最終的にはしっかりとした技術に繋がり、確実に成長を実感できるはずです。その一歩を踏み出すために実践しやすい方法をご紹介しますので、試してみてくださいね。
動作を分解して練習する
まず、ミラー操作に集中して練習しましょう。視野の確保や反射の使い方に注意を払いながら、ミラーの持ち方や角度を安定させることに力を入れます。
次に、片手で器具を持つ練習。スケーラーの持ち方や動かし方を意識して、安定した操作を目指します。
「全部ちゃんとやらなきゃ」と考えると混乱しやすいですが、動きをひとつずつ分けて覚えていくことで、少しずつスムーズにできるようになっていきます。
目を閉じてプローブとスケーラー操作の練習をする
目を閉じた状態で、プローブ操作をしてみましょう。視覚を遮断して、指先の感覚だけで動かすことで、触覚の精度がぐっと上がります!
抜去歯牙で植立模型を作って根面を触ってみたり、プラスチックの表面や紙を触ってみると、その感触の違いがはっきりと分かります。目を閉じることで、ただの表面の凹凸だけでなく、微妙なひっかかりやザラつきも感じ取ることができ、歯根表面のイメージトレーニングにも最適です。
「シャープニング」と「器具選び」を見直す
スケーリングやSRPで滑ってしまったりうまくいかない時は、スケーラーのシャープニングがきちんとできているか確認していますか?シャープニングをしっかりすることで、指先に伝わる感覚が代わり、歯石除去できる率も格段に上がります。「これ、いつシャープニングしたかな?」というスケーラーを使っていたら要注意!
手が疲れてしまう時や、なんだかしっくりこない…という時は、自分の手に合った器具かどうかを見直してみましょう。グリップ付きの器具や、口腔内に挿入しやすい形状のスケーラーを選ぶのも大事です。
自分に合った器具を見つけるためには、周囲のアドバイスを活用しましょう。
先輩に「おすすめのスケーラーは何ですか?」と気軽に聞いてみましょう。先輩方は多くの経験を積んでいるので、試行錯誤している時に役立つ情報を持っていることが多いです。また、他の医院や勉強会で会った人にも聞いてみると、新しい視点が得られるかもしれません。
ディーラーさんに相談するのもありです。ディーラーさんはさまざまなメーカーや製品に詳しく、商品の特徴や実際に使ったスタッフの感想なども教えてくれることがあります。自分ではなかなか見つけられない便利な器具を紹介してくれることもあるので、積極的に質問してみましょう。
どんな器具が自分の手にしっくりくるかは実際に使ってみないとわからない部分も多いので、いろんな人の意見を取り入れながら選んでみましょう!
姿勢・チェアポジションを見直してみる
技術がうまくいかないのは「姿勢が合ってないだけ」ということもあります。
アプローチの位置を変えてみてください。たとえば8時の位置から操作している場合、3時の位置から試してみることで、よりスムーズに作業が進むことがあります。
自分の座る椅子の高さや、患者さんのチェアの高さ、安頭台の向きなど、ほんの少し変えるだけで操作しやすくなることもあるので見直してみましょう。自分の操作姿勢を先輩や同僚に見てもらい、アドバイスをもらうのもおすすめです。第三者の視点で気づくことも多いので、積極的にフィードバックを受けましょう。
処置の流れが複雑なものはメモを貼っておく
処置の流れが覚えられない時は、付箋や小さな紙に「処置の流れ」を書いて、傍に置いたり貼ったりしておくのもありです。こうすることで、処置中に「次は何だっけ?」と焦ることなく、処置に集中することができます。
特に最初は、複雑な手順を完璧に覚えるのは難しいもの。「慣れ」と「全体の流れを理解すること」が、複雑な処置をスムーズに進めるためのカギです。何度も繰り返しやっていくうちに、全体の流れがだんだんと自然に身についてきます。最初からすべて覚えて完璧にやらなきゃ!と思わずに、メモに頼って、「焦らず、冷静に」を優先しましょう。
先生の癖や動き方を観察する
器具の受け渡しがスムーズにできないときは、先生の癖や動きを観察することで、受け渡ししやすいタイミングや渡し方が見えてきます。
たとえば、器具を「ぽんっ」と軽く置いて渡すと、先生が取りづらかったり、落としそうになったりすることがあります。私は、先生の手のひらにほんの少し“グッと”押しつけるように渡すようにしていました。こうすることで、「はい、渡しましたよ!」という感覚がしっかり伝わります。ちょっとした工夫ですが、先生とのテンポも合いやすくなり、スムーズなアシストができるようになります。
わからないときは、思い切って「今の渡し方、やりづらくなかったですか?」と聞いてみるのもアリです。意外と、丁寧にアドバイスをくれる先生が多いです。
先生がよく使う器具やバーの種類を覚えておくのもおすすめ。「次はこれかな?」と予測を立てて準備でき、次に渡すタイミングもスムーズになりますよ。
新しい材料や機械を取り入れる
たとえば石膏や印象材などの材料を手で練る作業は、慣れるまで難しいですよね。「不器用だな」と感じることが多い場面だと思います。
でも、今では自動練和も主流になってきています。手作業するところと機械を使うところをうまく使い分けることで、作業が楽になります。
材料や機械は日々進化しています。「もっと使いやすいものはないかな?」と感じたら、自分で調べたり、スタッフ同士で情報交換をしてみましょう。もし良さそうな材料や機械があれば、先生に提案してみて、取り入れてもらうのも一つの方法。使いやすい道具を活用することで作業のストレスを減らし、よりスムーズに業務をこなせるようになります。
練習時間を確保する
練習時間の確保は、技術を身につけるための大きなポイントです。私は、朝の時間を有効活用していました。具体的には、30分早く出勤して、スケーラーの操作やSRPの練習をしていました。始業前の静かな時間帯は、集中して練習することができるのでとてもおすすめです。
練習時間は、無理なく日常の中に組み込むことが大切です。朝の始業前や、午後診療が始まる前の15分だけ、勤務後20分間だけなど、自分のペースで練習できる時間を考えてみましょう。短時間であっても積み重ねが大きな力になりますし、集中して取り組むことで効果を実感できます。
日々の練習や工夫を積み重ねていくことで、どんな小さな努力でも、少しずつ自信がつき、技術も着実に向上していきます。大切なのは、焦らず自分のペースで進んでいくこと。無理に他の人と同じようにやろうとせず、自分のペースを大切にして進んでいくことで、必ず自分に合った方法が見つかるはずです。
そして、それが患者さんやチームへの貢献にも繋がっていきます。少しずつ進んでいくうちに、歯科衛生士の仕事の楽しさをより感じられる瞬間がきっと訪れます。楽しむ気持ちを大切にしながら、自分を信じて取り組んでいってくださいね。
実技が苦手でも、他にも活躍する場はある
ここまで、不器用さと向き合うヒントをいろいろとお伝えしてきました。
「いろいろ試してみたけど、やっぱり苦手かも」「できない自分に落ち込んでしまう」そんな気持ちになることも、きっとあると思います。
でも、それって決して「努力が足りない」わけでも、「向いていない」わけでもありません。誰にだって得意・不得意があって、それぞれ違った形でチームや患者さんの役に立てるのが、歯科衛生士という仕事の奥深いところです。
たとえば、患者さんへのTBIや声かけが得意な人。緊張している人にそっと寄り添える人。院内の空気をやわらかくしてくれる人。細かいことによく気づいてフォローできる人。そんな力も、日々の診療に欠かせない「技術の一つ」なんです。
手先の技術に向き合うことも大切だけど、それだけじゃない。「これは得意かも」「こういう場面なら自分らしくいられるかも」——そんな“あなたらしさ”を見つけて、それを育てていくことも、確かな一歩です。
ただ、「自分の得意なことって何だろう?」と考えても、一人では見つけられないこともあると思います。第三者の視点から、自分の強みや適性を整理することで、本当の得意なことが見えてくることもあるんです。
D.HITキャリココでは無料相談を受け付けています。実技の得意・不得意だけでなく、あなたの本当の適正や活躍できる場所について一緒に考えることができますよ。ぜひ、LINE登録をして申し込んでみてくださいね!
できないことばかりに目を向けずに、今できていることや、自分の中にあるやさしさや丁寧さに、ぜひ目を向けてみてくださいね。あなたの中には、きっと誰かの役に立てる力が、すでにあるはずです。