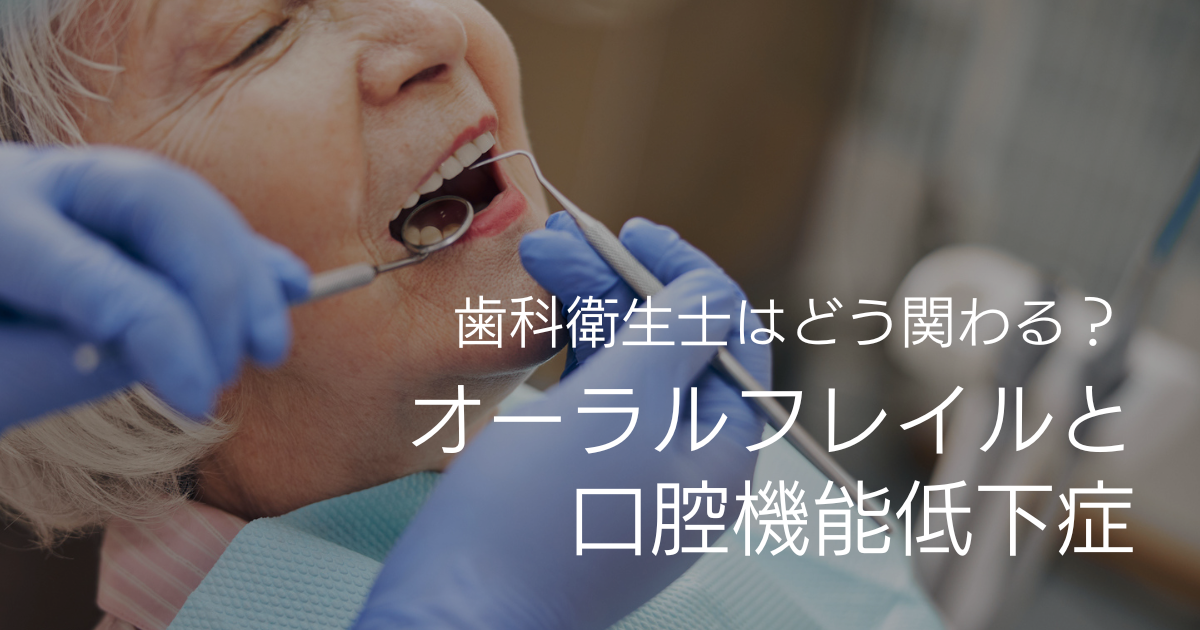「最近、うまく噛めない」「飲み込みづらくなった気がする」…高齢の患者さんから、そんな声を聞いたことはありませんか?
「歯が揃っているから大丈夫」「話せているから問題ない」と思っていませんか?
実は、高齢者の口腔機能の変化は目に見えにくく、気づかれにくいもの。しかし、見逃したままにしておくと、食事・会話・健康維持そのものに支障をきたす重大なリスクにつながります。
だからこそ、歯科衛生士に求められているのは、「歯」だけでなく“機能”そのものに目を向ける視点。そして、口腔機能の低下を早期に見つけ、的確に評価・支援する力です。
この記事では、高齢者の口腔機能の基礎知識から、評価方法、診療室での具体的な支援アプローチ、そして今後のキャリア展望までをわかりやすく解説します。明日のケアにすぐ活かせるヒントを、ぜひ見つけてください。
高齢者の「口腔機能」とは?
そもそも「口腔機能」とは、「食べる・飲み込む・話す・感じる・呼吸する」といった、口を使った日常的な動作を支える総合的な機能のこと。具体的には、次のような機能が組み合わさって、日々の生活が成り立っています。
- 咀嚼(そしゃく):食べ物を歯で噛み砕き、唾液と混ぜて飲み込みやすくする
- 嚥下(えんげ):噛んだものを安全にのどを通し、胃へ送り込む
- 発音:舌や唇、頬の動きによって、明瞭に言葉を発する
- 唾液分泌:口の中を潤し、乾燥や感染を防ぐ
- 感覚機能:熱い・冷たい・辛いなどを感じ取り、咀嚼や嚥下をコントロールする
高齢になると、これらの機能は加齢や筋力低下、慢性疾患の影響によって、少しずつ衰えていきます。
- 舌の動きが鈍くなり、うまく食べ物を口の奥へ運べなくなる(舌圧低下)
- 噛む力が落ちて、硬いものを避けるようになる(咬合力低下)
- 唾液が減り、口の中が乾いて食べにくい・話しにくい(ドライマウス)
こうした衰えが積み重なると、栄養バランスの偏りや、食欲低下、誤嚥性肺炎のリスクに直結し、結果として全身の虚弱(フレイル)や寝たきりにつながることもあります。
つまり、口腔機能は単なる「口の動き」ではなく、全身の健康・社会参加・生きがいにも深く関わっているのです。
ここでは、口腔機能低下の前兆ともいえる「オーラルフレイル」、そして正式な疾患として定義されている「口腔機能低下症」について、基本的な知識と、診療室や訪問の現場で活かせる具体的な評価方法を解説します。
オーラルフレイル
加齢に伴う口腔機能のわずかな衰えが、放置されることで徐々に全身の虚弱(フレイル)へとつながっていく状態
つまり、「噛む・飲み込む・話す」といった口の機能の軽微な衰えが、やがて栄養不足・活動性の低下・社会的孤立を招く——その入口になる、という考え方です。
近年、この「オーラルフレイル」という概念は、日本老年歯科医学会をはじめとする専門団体から注目され、介護予防や地域包括ケアの中でも重要なキーワードとなっています。さらに、保険診療の中でも「口腔機能管理」が導入されるなど、制度面でもその対応が求められるようになってきました。今や、歯科医療の現場においても“見逃してはならない変化”として位置づけられています。
- 硬いものが噛みにくくなった
- 食事中によくむせるようになった
- 滑舌が悪くなった、言葉がもつれる
- 口の中が乾きやすく、唾液が少ない
- 「食事が疲れる」「声がこもるようになった」といった自覚症状
こうした日常の小さな違和感の積み重ねによって、噛む力・飲み込む力・話す力がさらに低下していき、その結果、誤嚥性肺炎・低栄養・サルコペニアなど、全身状態の悪化につながるリスクが高まるのです。
重要なのは、オーラルフレイルは「まだ病気ではない」段階だということ。1つ1つは小さな違和感だから、患者さん自身が深刻に捉えず「まだ大丈夫」と放置してしまうことが多いんです。
だからこそ、歯科衛生士が早期に気づき、早期に支援できる領域なのです。
「最近、食事のペースが遅くなったな」「会話の中で、発音が不明瞭かも?」そんな小さな変化を、診療室での観察やちょっとした会話から拾い上げられるかどうかが、歯科衛生士に求められる力です。
「まだ大丈夫」を「今、サポートする」へ変えていく。オーラルフレイルへの理解と早期対応こそが、歯科衛生士の新しい専門性と言えるのではないでしょうか。
口腔機能低下症
加齢や疾患などを背景に、複数の口腔機能が一定の基準を下回っている状態
口腔機能低下症は、2018年に保険診療に正式に導入され、疾患として位置づけられたことで、歯科医院における評価と対応が強く求められるようになりました。
「なんとなく調子が悪い…」という曖昧な感覚ではなく、明確な数値や観察項目に基づいて診断されます。具体的には、以下の7項目のうち3項目以上が該当すると診断対象となります。
- 口腔衛生状態
…プラークの付着、舌苔など - 口腔乾燥
…唾液の減少、口腔内の粘つき - 咬合力の低下
…噛む力が弱くなる(義歯不適合含む) - 舌口唇運動機能の低下
…「パ・タ・カ」などの発音・動作の低下 - 発音の明瞭度低下
…聞き返しが増える、話しにくそうにする - 舌圧の低下
…舌で上あごを押す力が弱まる - 嚥下機能の低下
…飲み込みの遅れ、むせる回数の増加
これらの評価は、歯科医院や訪問歯科の現場でも実施可能です。特に、舌圧計やオーラルディアドコキネシス(ODK)といった簡便な検査器具があれば、チェアサイドでのスクリーニングも十分に行えます。
もちろん、すべての患者にフルセットでの評価が必要なわけではありません。重要なのは、歯科衛生士が日々の診療の中で、「あれ?」という変化に気づき、適切な評価・記録・医師への共有につなげる視点を持っているかどうかです。
- オーラルフレイル=予兆(グレーゾーン)
- 口腔機能低下症=基準を満たした疾患(診断が必要)
口腔機能の変化は、目に見えにくく、言葉にされにくいです。だからこそ、歯科衛生士はそのわずかな変化に気づき、生活を守る支援者として、重要な役割を担っているのです。「歯」だけではなく「機能」を診る歯科衛生士の力が、これからの歯科医療に求められています。
代表的な検査方法
口腔機能低下症の評価には、以下のような定量的な検査が使われます。
- 舌圧計(ぜつあつけい)
- オーラルディアドコキネシス(ODK)
- 咬合力測定
これらの検査は、「見えない口腔機能の低下」を「見える化」できる手段として使用していきます。現場での活用も進んでおり、歯科衛生士が補助的に関わることで、よりきめ細かな支援が可能になります。
舌圧計(ぜつあつけい)
舌の筋力を測定する機器。専用の小型風船を口の中(上顎)に当て、舌で押し上げた圧力を数値化します。30kPa未満は舌圧低下とされ、嚥下障害のリスク指標としても重要です。
オーラルディアドコキネシス(ODK)
「パ・タ・カ」の3音をそれぞれ一定時間繰り返し発音し、1秒間に平均何回発音できるかを測る検査。舌・唇・咽頭の運動機能を評価します。
- パ:口唇の動き
- タ:舌尖(舌先)の動き
- カ:舌根(舌の奥)の動き
基準値:6回/秒未満で低下と判断されることがあります。
咬合力測定
咬合力をガム型測定器や圧力センサー付きフィルムで計測します。咀嚼能力の指標として用いられ、義歯の適合状態や食事支援の方針決定にも活用されます。一般的に200N以下が低下の目安とされます(年齢・性別により異なる)。
- 「なんとなく元気がない」という曖昧な症状の裏付けが取れる
- 口腔機能低下の進行度や変化を定期的に追える
- 患者自身にも状態を「数値」で伝えられ、生活改善の動機づけにつながる
- 医師・歯科衛生士・スタッフ間で共通の判断材料を持てる
つまり、検査結果と通して「伝わる支援」「納得できるアドバイス」が可能になります。「歯」だけでなく「機能」を診る時代。歯科衛生士が日常の診療の中に「気づき→評価→支援」の流れを作っていくことができるのです。
歯科衛生士ができる口腔機能アプローチ
「評価はしたけれど、その先どう支援すればいいのか分からない…」そんな迷いはありませんか?高齢者の口腔機能低下に気づいても、歯科衛生士として「具体的に何をすればいいのか」悩む場面は少なくありません。実は、診療室という限られた空間の中でも、歯科衛生士だからこそできる支援がたくさんあります。
口腔機能を維持・向上させるには、「早期の気づき」と「継続的なアプローチ」の両輪が必要です。評価して終わりにするのではなく、トレーニングや指導、院内連携を通じて、患者の「できる力」を引き出す支援が大切です。
ここでは、次の3つの視点から、歯科衛生士ができる具体的な支援方法を紹介していきます。
- チェアサイドで行うトレーニング
- 日々の生活を見直すサポート
- 院内でのチーム連携
チェアサイドで行うトレーニング
診療中の限られた時間でも、その場で実践できるトレーニングがあります。患者さんのモチベーションを引き出しながら、日常生活に役立つ機能改善をサポートできるのが、歯科衛生士の強みです。
パタカラ体操
口唇・舌・咽頭の動きを鍛える基本のトレーニングです。「パ・タ・カ・ラ」と大きく発音することで、発音・嚥下・咀嚼に関わる筋肉を刺激できます。
舌体操
舌を上下左右に動かしたり、口の中で円を描くように動かしていくトレーニングです。舌の柔軟性と筋力が上がることで、飲み込みやすさ、発話の明瞭度の向上が期待されます。
あいうべ体操
口輪筋をメインに口腔周囲筋を鍛え、口呼吸を鼻呼吸にするためのトレーニングです。唾液の分泌を促進し、口臭、むし歯、歯周病予防に役立ちます。
どの体操も器具は不要で、チェアタイムの合間にそのまま実践可能です!「今日から、お家でもやってみてくださいね」と伝える一言が、患者さんの変化を生むきっかけになります。
日々の生活を見直すサポート
口腔機能を守るには「生活の質」に働きかける視点も大事にしましょう。歯科衛生士は、患者の習慣に介入できる数少ない存在。日々の行動の中に、改善ポイントが隠れています。
義歯の清掃指導
「見た目」だけでなく、「清潔を保つことが肺炎や炎症の予防につながる」といった意識づけが効果的です。
咀嚼指導
「よく噛んでくださいね」ではなく、「1口30回を目安に噛むと消化も良くなって、脳も活性化しますよ」など、具体的に伝えると継続されやすくなります。
姿勢
診療中に「足が浮いていませんか?」「背もたれに頼りすぎていませんか?」などの声かけを行い、正しい座位姿勢の重要性を伝えましょう。姿勢が整うだけで、咀嚼力や嚥下反応が大きく改善することもあります。
院内でのチーム連携
診療室内でのアプローチをより効果的にするには、院内スタッフとの情報共有・連携が不可欠です。どんなに些細な変化でも、気づいたら歯科医師や他スタッフと共有しておくことで、治療や補綴設計、リコール方針の見直しに直結することがあります。
たとえば、
- 「舌圧が弱そう」
- 「義歯が合っていないかも」
- 「咀嚼が片側に偏っている」
こういった臨床中の気づきは、すぐに歯科医師に報告しましょう。補綴の再評価や、舌圧計などを使った検査の提案につながるかもしれません。
また、患者さんとの会話の中で得た情報も重要です。「最近むせるようになった」「硬いものを避けている」などは、口腔機能低下のサインかもしれません。気づきを院内で共有することが、チーム医療の質を底上げします。
診療室内でも歯科衛生士は口腔機能を「守る」「高める」「伝える」存在として、大きな役割を担っています。患者さんの変化をキャッチし、的確なアプローチを積み重ねることが、生活の質を支える本質的な支援につながります。
介護の現場で確認すること
訪問歯科や介護施設では、診療室とは異なり、患者さんの生活そのものに近い環境で関わることができます。その分、「目に見える口腔」だけでなく、全身状態や生活動作も含めた“機能全体”への観察力が、歯科衛生士には求められます。
特に重要なのは、日々の状態の変化を見逃さないことです。口腔機能の衰えは、全身の虚弱(フレイル)の一部であり、「他の機能も同時に低下していないか?」という視点が欠かせません。
- 食事のペースが遅くなっていないか?
- 食事中にむせたり、飲み込みづらそうな様子はないか?
- 義歯を入れていない時間が増えていないか?
- 会話の中で、言葉がもつれる・息が続かないといった変化はないか?
こうした“いつもと違う”小さな違和感は、介護スタッフやご家族も気づきにくいことがあります。歯科衛生士がプロとして観察し、「ちょっとした変化」に敏感であることが、重大な低下の兆候を見つけるカギになります。
口腔機能の状態は食事中に最もリアルに表れます。
- 食材を噛み切れているか
- 飲み込む前に長く咀嚼していないか
- 途中で食べるのをやめていないか
- スプーンや箸を持つ手に力が入っているか
こうした観察ポイントから、口腔機能の衰えだけでなく、認知・筋力・意欲など他の側面も見えてきます。
ときには、食事内容そのものが課題になっていることも。硬すぎる、パサついている、滑りすぎているなど、食形態と口腔機能のミスマッチが、摂取量や誤嚥リスクを高めているケースもあります。
歯科衛生士は、「食べる行動=機能の最前線」としてとらえ、ただの口腔ケア担当ではなく、「食支援のパートナー」として、施設内でも重要な役割を担える存在なんです。
歯科衛生士として知っておきたいスキルやキャリア展望
「私たち歯科衛生士に、これから求められる力って何だろう?」と考えたことはありますか? 実は今、歯科衛生士の現場には“ある大きな変化”が訪れています。
それは、「スケーリングする人」から「機能を支える人」へのシフトです。
超高齢社会が進む中で、単に歯をきれいにするだけでは、患者の生活を守ることができなくなってきているのも事実です。「食べる、話す、飲み込む」そんな日常の当たり前を支える「口腔機能」こそが、今後の歯科医療の中心軸になっていくのです。
そんな時代の流れを踏まえて、“今、歯科衛生士が身につけておきたいスキル”や、“医院にとっての具体的なメリット”を紐解いていきます。
これから必要になる「見て・支えて・伝える力」
口腔機能低下症は、単に「年齢のせい」では済まされません。 機能が下がる過程を早期にキャッチし、維持・改善に向けた関わりを行うことが、歯科衛生士にとって欠かせないスキルです。
- 発音・咀嚼・嚥下などの観察力
- チェアサイドでできる機能トレーニングの提案力
- 生活習慣や義歯管理への具体的な指導力
- 歯科医師やスタッフとの情報共有・連携力
「診療中のわずかな会話から異変に気づける」「その場で必要な支援を提案できる」…こうした力は、特別な資格がなくても、日々の実践から育てていける専門性です。
高齢社会が進む中、歯科医院には「治療中心から予防・管理中心」へのシフトが求められています。その中核を担うのが、歯科衛生士による口腔機能の「観察・評価・支援」のループ構築なんです。
たとえば、咀嚼力が落ちて食事量が減った高齢者に対し、ただ義歯の清掃指導をするだけでは根本解決にはなりませんよね。舌圧や咬合力、姿勢や習慣まで含めて“生活を診る”視点があってこそ、予防や支援が成立します。
だからこそ、これからの歯科衛生士には、「見て」「支えて」「伝える」力が欠かせません。
口腔機能低下症の算定が保険適用されたように、今後も制度面での支援は増えていくと考えられ、“できる歯科衛生士”の価値はますます高まるでしょう。院内でも、「この患者さん、舌圧落ちてるかも」「パタカラやってみませんか?」といった声かけができる歯科衛生士は、治療の質を底上げする“チームの要”として、医師や患者から信頼される存在になります。
歯科医院が「地域の健康拠点」になる時代へ
今後、歯科医院は「歯を治す場」から、「地域の口腔健康を守る拠点」としての役割を担っていく流れが加速します。その中で、地域の高齢者・在宅患者・予備軍の方々とつながる“接点の創出”を担えるのは、他でもない私たち歯科衛生士です。
歯科衛生士が口腔機能支援に関わり、院内外で積極的に行動することは、医院全体にも大きなメリットをもたらします。
- 患者との信頼関係が深まり、自然な口コミにつながる
- リコールやメンテナンスの質が上がり、通院継続率の向上につながる
- 地域包括ケアや他職種との連携が生まれ、医院の認知・信頼が上がる
- 在宅・訪問ニーズへの対応準備としても役立つ
歯科衛生士が地域と積極的につながることで信頼関係ができると、「ここの医院は、話をちゃんと聞いてくれる」「些細な変化にも気づいてくれる」と感じた患者さんは、他の人にもすすめてくれるようになります。また、“自分のことをしっかり見てもらえている”という実感は、リピートにもつながります。地域包括ケアや多職種との連携において、「歯科医院からケア会議に情報提供してくれる」「専門的な口腔支援の相談ができる」そんな立ち位置を確立することで、地域内での存在感が高まります。そして、将来的な訪問診療対応や、施設との連携を見据えたとき、歯科衛生士が地域と関係を築いておくことは、医院の成長戦略にもつながります。
たとえば、こんな提案が院内から自然に出てくると、医院のあり方は確実に変わっていきます。
- 「口腔機能チェック会、定期的に開催しませんか?」
- 「“むせる”って言ってた◯◯さん、次回も気にして見ていきましょうか?」
- 「地域ケア会議に、歯科から情報提供してみませんか?」
こうした動きが広がれば、医院全体が“健康を守る場所”としてのブランドを築くことができます。歯科衛生士がその役割を担い、地域と医院をつなぐハブとなることこそが、これからの歯科医院経営のカギを握っています。
そして今後、選ばれる医院になるために必要なのは、設備や技術だけではなく、 “地域にとって何ができるか”を考え、行動できるスタッフの存在です。そんな主体的な提案ができる歯科衛生士は、地域の中でも評価され、活躍の場を広げていくことができます。
まとめ
高齢者の口腔機能支援は、これからの歯科衛生士に欠かせない視点です。超高齢化が進む中、「食べる・話す・飲み込む」といった機能の低下は、健康寿命やQOLに大きく関わっています。
高齢者の口腔機能低下は、「気づいたときには進行している」ことも少なくありません。
だからこそ、咀嚼や嚥下、発音などの異変に早期に気づき、その場での評価・声かけ・支援へとつなげる力が、いま歯科衛生士に求められているんです。
これからの時代、歯科衛生士は「お口の掃除をする人」ではなく、患者の生活を守る“口腔機能のマネージャー”としての役割がますます重要になっていきます。
私自身、臨床現場で接した方から「もう、歳だからね」と言われることが多くあります。もちろん、加齢に逆らえない部分はあると思います。それでも、ほんの小さな違和感から大きな気づきを得ることがあります。患者さんのこれからを「支えるってこういうことか」と実感することもたくさんあります。
一人ひとりの患者の変化に「気づき、関わり、支える」その積み重ねが、診療室の価値を高め、地域の中で「必要とされる歯科医院づくり」にもつながっていくはずです。
まずは、目の前の患者さんにひとつ、「声をかけること」から始めてみましょう。その一歩が、あなたのケアを“もっと深く、もっと意味のあるもの”に変えていくはずです。
また、口腔機能支援という新しい役割で、あなたの経験がもっと活かせるかもしれません!経験を活かしてキャリアを広げたいと考えているなら、D.HITのキャリココを活用するのもありです!まずは、無料相談で詳しい話を聞いてみてくださいね!
↓高齢の患者さんとのコミュニケーションの取り方はこちら♪