医療的ケア児や重度障害をもつ子どもたちにとって、「通院する」という行為自体が大きな負担になることがあります。だからこそ、自宅という安心できる環境で歯科診療を受けられることには、大きな意味があります。
小児在宅歯科診療は、「通院が難しいから仕方なく訪問する」という代替的な手段ではありません。子どもたちの発達や生活の質を支える、必要不可欠な医療のひとつです。
私が小児在宅歯科診療を始めたのは、自身が勤務していた歯科医院へ依頼があったことがきっかけでした。小児の在宅と聞いて、「なにそれ?」というのが最初の感想です。障害や病気があっても通院してくる子どもも中にはいるため、「連れて来れないのかな?」と思っていました。
そこから、在宅治療中で「通院できない」子ども達の存在を知り、必要とする人達のために歯科が関わりを持っていかないといけないと気づきました。全ての子ども達に歯科医療を届けたい!と思うようになり、今でも活動を続けています。
医療的ケアを必要としながらも在宅で生活する子どもたちに、歯科として関わりを持てること、そして、子ども達の成長を一緒に見守っていけることが本当に素敵な仕事です。
前編では、小児在宅歯科診療の基礎知識や、対象の子どもたちの特徴、歯科衛生士が果たす役割についてお伝えしました。まだの方はぜひ【前編】からご覧くださいね。
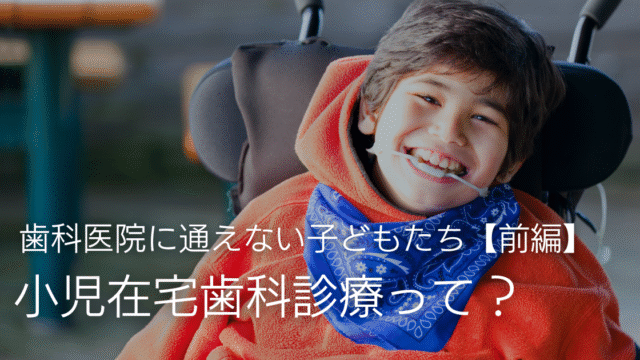
後編では、実際の小児訪問診療の流れや気を付けるポイント、現場で感じるやりがいや葛藤について、私自身の体験をもとにお届けします。
小児在宅歯科診療の「なぜ必要なのか」から「どう関わっていけるのか」まで。歯科衛生士として、チーム医療の一員として、子どもとそのご家族にどう寄り添えるのか、その視点も一緒に考えていただけたら嬉しいです。
在宅歯科診療の流れと準備
小児在宅歯科診療は、「その場で診て終わり」ではありません。安全なケアを実現するためには、訪問前の情報収集、当日の柔軟な対応、訪問後の医療者間での共有まで、一連の流れすべてに意味があります。実際、私が行っている小児訪問での流れを元に、詳しくお伝えしていきます。
訪問前|情報収集と準備を念入りに
医療的ケア児の場合は、口腔内だけでなく全身状態を見ながらの判断が欠かせません。「この子の生活に、どう歯科が関われるか?」を考えながら、1回1回の訪問に向き合う必要があります。そのための情報収集と準備は、毎回とても念入りに行っていました。
歯科では聞きなれない病名や、聞いたことのない障害を持っている子どももいますし、1つだけの疾患というよりは複数が絡み合っていることが多く…事前に情報を得て勉強しておかないと、分からないことが多いです。安全な在宅歯科診療の第一歩として「行く前の準備」をしておく必要があります。
- 対象の子どものバイタルサイン
- 既往歴
- 使用している医療的デバイス(人工呼吸器・胃ろうなど)
- 自宅や施設の環境
把握できる情報はすべて、事前に確認します。確認方法は、訪問看護師さんやご家族からの、問診票やヒアリング。この段階からすでに“チーム医療”は始まっており、準備の質がそのまま診療の質に直結すると言ってもいいでしょう。
「事前問診」を必ず行い、主訴やご家族のご希望(口腔ケアをしてほしいなど)を把握しておきます。訪問してから「あれがない」「これがほしかった」とならないよう、器具の準備をしていきます。「当日の体調」や「ケア時の注意点」を共有することも大切です。
訪問に合わせて、体調やスケジュールを調整してくださるご家族も多いです。できるだけ、訪問日に診察・診療を済ませられるように、想定される治療のあらゆる可能性を視野に入れ、準備をしています。
訪問中|口腔ケアや治療時に注意すること
小児歯科で、「もう少し頑張れそう?」「もうちょっとやってみる?」と子どもに声かけること、ありませんか?
小児在宅歯科診療では、その見極めが重要になってきます!
無理は禁物!
子どもの様子を観察し、「今日はどこまでできそうか」を見極めることから始まります。歯磨き、粘膜ケア、舌の清掃、器具の調整、口腔マッサージなど、状態に応じて施術内容を柔軟に選択します。『無理は禁物』です。調子が良さそうに見えても、身体のどこかに炎症があったり、病気があったりする子ども達です。私自身、この”もう少し”の判断はすごく難しいなと感じる部分でした。「無理をさせない」「しんどくならない」そのラインを見つけ、口腔ケアを慎重に進めていきます。
吸引のタイミングや姿勢の工夫
医療的ケア児の場合は、診察中、吸引とのタイミング調整や姿勢の工夫が不可欠になります。
歯科衛生士でも研修を受ければ喀痰吸引は可能ですが、子どもの口腔内は狭く繊細なため、慣れているご家族や訪問看護師さんに吸引をお願いした方が、子どもにとって負担が少ないのが現実です。処置中はそうした連携を取りながら進めます。ご家族や訪問看護師さんの判断基準やタイミングを知り、覚えて学んでいきました。
「苦しい」「痛い」と言葉にして伝えられない子もいます。子どもの様子や表情からそれを汲み取れる人が側にいる状況で治療を進めることは、子どもが安心して治療を受けられる環境作りでもあり、歯科医院側の安心材料にもなっていたと感じます。
訪問後|報告・医療者間フィードバック
在宅診療が終わった後は、「終わり」ではなく「共有の始まり」です。現場で見えた小さな変化や気づきは、医師や看護師、リハビリ職など他の専門職へ必ずフィードバックを行います。
「歯石除去後に熱が出た」と言われたこともあります。酷くなれば入院です。
口腔内の所見・状況・治療内容など、共有していくことが必須です。診察後、変化があれば、対応してもらえるようにしておくことも大事ですし、事前に近況を知ることで、無理させないような選択をすることもできます。
前例がないと言われる子ども達も多く、「よく分からない」…そんな状況なこともあります。分からないことが多いからこそ、多くの情報共有が必要だと思っています。
医療的ケア児への対応ポイント
小児在宅歯科診療において、医療的ケア児への対応には、通常の小児ケアとは異なる“医療的視点”が求められます。呼吸状態の確認、誤嚥リスクへの配慮、バイタルの変化など、命に直結する要素に向き合う現場では、歯科衛生士自身にも冷静な判断力と連携力が必要です。
ここでは、現場で意識したい3つの視点を紹介します。
最低限の医療知識を持つ
医療的ケア児は呼吸器や栄養チューブを使用しているケースも多く、体位変換ひとつで呼吸状態が悪化する場合もあります。歯科衛生士として専門外であっても、最低限の医療知識は持っておいて、「この姿勢でケアして大丈夫か?」「気道は確保されているか?」「誤嚥のリスクはないか?」という視点が必要になります。
- 気道管理
気管切開チューブや人工呼吸器を装着している場合、体位によって呼吸がしづらくなることがあるため、首の角度に配慮し、呼吸数の変化・胸郭の動き・痰の音に敏感になる必要があります。 - 誤嚥予防
嚥下反射の弱い子や、唾液がたまりやすい子は、少量の水分や分泌物でも肺炎のリスクにつながります。体位がとても重要で、子どもの状況によってベストな体位も変わります。吸引が必要な子には、吸引のタイミング・操作の声かけも重要。 - 逆流や嘔吐を誘発する恐れ
食事後30〜60分は避けると安心。 - バイタル変化への対応
診療中に顔色の変化、咳、意識レベルの低下が見られた場合には、すぐに中断し、看護師や医師と連携します。 - 鼻カニューレの位置やSpO₂(経皮的酸素飽和度)への配慮
歯科衛生士がモニターの数値を直接扱うことはありませんが、「見て気づく」「異変を医療者に伝える」という意識を持つことが、安全につながります。
子どもの全身状態を読む力、医療的状況を理解した上での行動判断は、歯科衛生士にとって“命を預かる現場”で求められる重要なスキルです。
家族の緊張を和らげる“安心感の伝え方”
医療的ケア児を育てるご家族は、常に「急変が起きたらどうしよう」「この人に任せて本当に大丈夫か」という緊張感のなかで暮らしています。小児在宅歯科診療でも、歯科衛生士の言葉や所作ひとつで、その安心感は大きく左右されます。だからこそ、技術だけでなく、“任せても大丈夫”と思ってもらえる空気感が何より大切なのです。
- 笑顔で挨拶する
- 動作はゆっくり
- 目線は低く
- 説明は短くわかりやすく
このような細かな配慮の積み重ねが、言葉以上に「大丈夫ですよ」というメッセージになります。機械音や吸引の音などが多くなる場面では特に、ご家族の緊張が高まりやすいため「今◯◯しますね」「終わりましたよ」と、段取りを見せる“実況中継のような声かけ”が安心につながります。
不安に思っていることを口に出せる雰囲気づくりも大切です。ご家族が何かを聞いたときには、否定せずまず受け止め、そこから一緒に答えを考える姿勢を見せることで、信頼関係が築かれていきます。専門職としての対応力と、人としての“寄り添う力”の両方が求められる現場になります。
「やってあげたい気持ち」が空回りしないために
丁寧にやってあげたいという思いが、時に子どもや家族の負担になることもあります。
現場に入ると、どうしても「もっときれいにしてあげたい」「しっかりケアしてあげなきゃ」という気持ちが湧いてきます。子どもが無表情だったり、言葉で反応できなかったりする場合、つい「頑張らなきゃ」と力が入ってしまうことも少なくありません。
ですが、子どもの体調が不安定だったり、機嫌が悪かったり、家族が疲れていたりする日もあります。口腔ケア中に咳き込みやすい子に対して、完璧な清掃を目指してしまうと、本人が苦しくなるばかりか、ご家族も「これ以上無理させないで」と感じてしまうかもしれません。
大切なのは、“完璧なケア”ではなく、“その子に合ったケア”。思いやりと冷静さのバランスが問われる、繊細な現場です。“今、この子にとってちょうどいいケア”を、その日そのときの状態に合わせて、必要なことだけをシンプルに、安全に行うことが、結果的に子どもと家族にとって最善になることも多いんです。
「丁寧にやる」ことと「無理をしない」こと、そのバランスを見極める力こそが、現場で求められるプロとしての在り方だと感じます。
在宅現場で感じるやりがいとリアルな葛藤
小児の在宅に関わる中で、嬉しいこともあれば、つらさに押しつぶされそうになる日もあります。「ありがとう」と声をかけてもらえるたびに救われる一方で、「もっと何かできたはずではないか」と、もやもやとした気持ちが残ることもありました。
理想だけでは続けられないのが在宅の現場です。ですが、子どもやご家族の笑顔に出会えた瞬間が、また一歩を踏み出す力になっています。
今回は、そんな、きれいごとでは語れない現場のリアルを、率直にお伝えしたいと思います。
感謝される一方で、無力感を抱く瞬間も
「ありがとう」の言葉に救われる一方で、「本当にあれでよかったのだろうか」「もっと何かできたのではないか」と自分を責めてしまうこともあります。
医療的ケア児は、体調が些細なことで変わるため、歯科衛生士としてできることの限界を痛感する場面もあります。命に関わるからこそ、責任の重さに押しつぶされそうになることもあります。
それでも、子どもの笑顔やご家族の感謝の言葉が、「やってきてよかった」と思える力になります。私にとって、それが“続ける理由”のひとつです。
続けるために必要なのは“理想”より“覚悟”
小児の在宅は、「誰かのために」「社会のために」といった理想だけでは続けられません。目の前の子どもが苦しそうにしていたり、ご家族が疲弊している様子を見るたびに、「本当に自分にできることは何だろう」と悩みます。そんなとき、自分の中で支えになるのは“覚悟”です。完璧にできなくても、逃げずに向き合い続ける勇気が必要です。
そしてもう一つ大切なのが、自分を守るセルフケアの視点。小児訪問歯科に携わっていると、担当しているお子さんが亡くなることもあります。短い時間の中でご家族と関わり、「この子が笑ってくれたのは、あの日が最後だった」「この子が人生を全うするのに、自分は少しでも力になれただろうか」と落ち込む日もあります。そういった感情を抱え込みすぎないよう、仲間に話したり、自分の気持ちを整理したりしてセルフケアすることも重要です。
小児在宅歯科診療は、やりがいと同時に孤独やプレッシャーとも向き合う場面があります。理想ではなく、覚悟を持ち、自分自身を大切にしながら、現場に立ち続けることが求められます。
歯科衛生士として“医療職”に負けないために
小児の在宅医療は、歯科単独で完結するものではありません。小児の在宅では、医師・看護師・リハビリ職など、複数の医療職と連携してはじめて、一人の子どもに対する「安全」で「安心」なケアが成り立ちます。私たち歯科衛生士も、この“チーム医療”の一員として、自分の役割を理解し、連携の中で力を発揮していくことが求められます。
とはいえ、現場に出始めたころは、戸惑うことも少なくありませんでした。
正直、医師や看護師が話している内容がまったく理解できない場面も多々ありました。専門用語が飛び交い、何のことを話しているのかすら分からない…。「分からないままにはしたくない」と思い、メモした単語を帰宅後にひとつひとつ調べ、ノートにまとめていました。最初はまるで学生のようでしたが、その積み重ねが、今の自信につながっています。
そんな経験を経て感じたのは、歯科衛生士だからこそ現場で見えてくる視点が必ずあるということです。口腔状態から全身状態のサインをいち早くキャッチしたり、子どもの表情や動きから「今日はこの姿勢が楽そうだな」と気づいたり、口の専門職である私たちだからこそ届けられるケアがあります。
大切なのは「歯科衛生士だからここまでしかできない」と自分で線を引いてしまわないこと。医療行為には法的な範囲がありますが、それは専門外だからと距離を置くのではなく、「わからないなら学ぶ」「必要なら聞く」「チームに貢献する」という姿勢が、他職種との信頼を築く第一歩になります。
知識不足を痛感し、落ち込む日もありました。それでも、「この人なら安心」と思ってもらえる存在を目指して、学び続ける姿勢が大事です。
「それでも私はやってよかった」と思えたこと
不安や葛藤を抱える日々の中でも、子どもやご家族の笑顔に出会える瞬間は、何ものにも代えがたい喜びとなります。ご家族から、「あなたが来てくれると安心します」「本当に助かっています」といった言葉をいただいたとき、歯科衛生士としての自分の存在が誰かの支えになっていることを強く感じます。
歯が抜けたときに一緒に驚いたり、虫歯の予防ができたことを喜び合ったり、摂食・嚥下機能の変化をともに見守ったり…成長を一緒に感じながら、小さな関わりがその子の人生の一部になることに、大きな意味があると感じています。
現場での積み重ねは、支援の質を高め、専門職としての信頼にもつながっていきます。困難な場面があっても、「やってよかった」と思える瞬間があるからこそ、私はこの仕事を続けることができています。
まとめ
医療的ケア児や重度障害をもつ子どもたちは、外出一つにも医療機器や多くのサポートが必要なことが少なくありません。そうした家庭にとって、自宅で専門的な歯科ケアを受けられることは、命を守るだけでなく「生活を守る」手段でもあります。
小児在宅歯科診療は、子どもたちとそのご家族が“自分らしい日常”を送るために必要な医療であり、「その子の生活の場」である自宅で、安心して受けられる医療のかたちです。
子どもたちは成長とともに、歯が生え変わり、食べ方や嚥下機能が変化していきます。虫歯の予防や口腔機能の発達支援、摂食嚥下など、未来の健康に直結する重要なテーマです。だからこそ、私たち歯科衛生士がこのタイミングで介入できることには大きな意味があります。
ご家族にとっては、「誰かが来てくれること」「専門職に相談できること」が、精神的な支えとなり、孤立感を減らす効果もあります。小児在宅歯科診療は、単なる医療処置にとどまらず、社会とつながる窓口のひとつでもあるのです。
単なる技術ではなく、「共に育ち、共に生きる」医療です。成長をそばで見守り、変化を共有し、そんな人間としての関わりが、私たち歯科衛生士にできる最大の支援なのだと感じます。
小児在宅歯科診療という選択肢に興味が出てきたなら、実際に「自分に合う関わり方は何か」「どう準備していくか」を考えることが大切です。もし「キャリアとしてどう活かせばいいかわからない」という方は、D.HITの「キャリココ」がおすすめ。あなたの現状や経験から、あなたに合ったキャリアをご提案します!
👉D.HIT公式LINEをチェック✅








