HSPって、ご存知でしょうか。最近になって広く知れ渡るようになってきた言葉です。自分もHSPかもしれない…と思っている歯科衛生士さんも多いのではないかと思います。
HSPは「他者の気持ちに寄り添える仕事と相性がいい」と言われているけど、実際歯科衛生士はどうなのでしょうか?
筆者も、歯科衛生士として働き始めてから、自分がHSPなのではないかと気づいた一人です。私の場合、HSPであるがゆえのメリットも多くありましたが、デメリットで辛くなってしまい、いくつかの医院を経たのち、最終的に臨床歯科衛生士を一度離れるという決断をしました。
今は臨床ではない新たな働き方を見つけ、また歯科衛生士として誇りをもって働くことが出来ていますが、もちろん、臨床でも工夫次第で、HSPの良さを最大限に活かしながら働くこともできると思っています。
HSPが歯科衛生士として働きやすい環境とは何か、私の経験を元に、考えてみたいと思います。
HSPの人は歯科衛生士に向いている?
まずは、HSPだからこそ、歯科衛生士という仕事に向いている!と私がメリットに感じていた面について、お伝えしたいと思います。
- 些細な変化に気づきやすい
- 物事を深く考えられる
- 感受性が強く、共感力が高い
- リスク回避がうまい
些細な変化に気づきやすい
HSPは常に周りにアンテナを張っているため、患者さんの様子や体調などの変化に気が付きやすいところがあります。
たとえば、よく来ている患者のおばあさんを見て「なんだかいつもより暗い気がする…」と思い、声をかけてみると、最近足を痛めてしまっていた…なんてことや、なんだかちょっとソワソワしている患者さんに話しかけると、「実は今日歯磨きしてこれてなくて申し訳なくて…」という話が聞けたり。
ちょっとしたことかもしれませんが、患者さんの些細な変化に気が付けるからこそ得られた情報です。足を痛めたというおばあさんは出入口近くのチェアに案内する、歯磨きを忘れてしまった患者さんには治療の前にクリーニングをするなど、そういったちょっとした情報から、患者さんのために出来る事というのはたくさんあります。
「雑談」は、患者さんとの信頼構築のために欠かせない、大切なコミュニケーション。HSPは患者さんの様子や体調などの変化に気づきやすいため、患者さん目線での雑談が広げやすいと思います。患者さんが言おうか迷っていることや、患者さん自身は気づいていないクセなどにもよく気づけるため、より密接な信頼関係を築くことができます。
また、HSPは細かなことにも気づきやすく、先読みをする能力に長けています。周りによく目がいくため、「気が利くね」とよく言われるという方も多いのではないでしょうか?たとえば資材の在庫がなくなりそうになっていることや、次の患者さんの器材準備など、他の人よりも素早く気づき、先回りした行動をすることが得意です。そのため、「気が利く」と評価されることが多いようです。
物事を深く考えられる
HSPの特徴の一つに、「物事を深く考えられる」というものがあります。この思慮深さは、患者さんへの歯科保健指導にも活かすことができます。
患者さんのお話を聞き、状況や環境を深く考え、このままでは歯周病や虫歯になってしまうかもしれないなど、その先に起こりうることを深く考察し予測できるので、患者さんに合ったより良いアプローチをすることができます。
歯磨き指導も、ただ「歯磨きしてください」と言うだけではなく、仕事の都合や小さいお子さんがいるなど、一人ひとりの状況を深く考えて提案することが得意なため、より患者さんに寄り添った指導をすることができるのです。
感受性が強く、共感力が高い
HSPは感受性が強く共感性が高いため、患者さんに「寄り添う」ことが得意です。患者さんの考えや辛さ、痛みに、より共感することができます。
共感できるからこそ、患者さんが訴える痛みや辛さを「そうですか」だけで流さず、より親身になって話を聞くことができたり、一緒に対策を考えることができます。患者さんとお話ができる時間は長くはないですが、その短い時間の中でも患者さんの思いに共感でき、信頼関係を築きやすいのは、HSPの強みだと思います。
患者さんとのコミュニケーションのコツについてはこちら

リスク回避がうまい
HSPは慎重で情報収集能力が高いため、危険やリスクを察知しやすく、リスクを回避する能力が高いことが多いです。そのため、
「この器具、取り出しにくい位置にあるから、そのうち落としてしまいそうだな…」
「コードが出ていて、足に引っ掛かりそうになっちゃうな。なにかできることはないかな」
など、医院内で起きそうなヒヤリハットにいち早く気づき、対策を考えたり、提案したりすることができます。
HSPって、自分ではついネガティブに捉えてしまうけど、悪いことばかりじゃないんです。本人としては当たり前にやっていることでも、実は当たり前じゃない。1つの能力として、強みとして、歯科衛生士の仕事に活かすことができているはずだと思います。
HSPの筆者が歯科衛生士で苦労したこと
強みになる一方、HSPの特性がマイナスとして出てしまうこともあります。私自身が苦労したことを含め、HSPがデメリットになる場面についてお話しします。
患者さんの負の感情も自分事に捉えてしまう
共感性が高いからこそ患者さんの気持ちに寄り添うことができるのはメリットですが、その反面、共感性が高いがゆえ、患者さんの「痛い」「辛い」「苦しい」といった負の感情にも共感してしまうのがHSPの辛いところです。
歯科医院って、痛いところの治療をするために訪れている患者さんが多い上、歯の治療に対して恐怖心を持っている患者さんも多いですよね。治療中の患者さんはどうしても苦しい表情になったり、辛そうな声を上げる事もあります。共感性の高いHSPは、それをさも自分事のように感じてしまうのです。これは、HSPでない方にとっては、理解し難い感覚かもしれません。
筆者は、そういった患者さんからの負の感情を受け入れすぎてしまった結果、自分のメンタルを壊してしまいました。診療補助をしているだけなのに、なんだか自分まで治療されているような、痛みがあるように感じてしまう時があり、また患者さんが痛そうな表情をすると、「痛くしてしまって申し訳ない」という罪悪感が出てきてしまうこともありました。治療しないことには治らないから仕方ないし、自分が悪いことをしているわけではないのに、患者さんが痛そうにしているのは自分のせいだと思いこみ、苦しくなってしまいました。
物音や周囲に敏感なため疲れやすい
タービンやバキュームの音、器具を準備するガチャガチャ音、患者さんを案内する声…歯科医院にはたくさんの音があふれています。特にタービンや口腔外バキュームは、とても大きな音ですよね。
HSPは、五感に敏感なことが多いです。聴力も例外ではなく、とても音に敏感な人がいます。
サクション等大きな物音がしている中で、院長の指示を聞き、患者さんの声を聞き…向こうでは先輩が器具を片付けている音がして、受付からは誰か患者さんが来た音、さらには外で車が通過した音、子どもが待合室のおもちゃで遊んでる音…。
周りにアンテナを張り続けている分、そうやって周りの音から色んな情報を読み取りすぎてしまうがために、情報過多を起こしてしまい、疲れてしまうことがあります。
私が特に苦手だったのはやはり、大きな音です。誰かが器材の乗ったトレーを落としてしまった時のガシャン!という音に対し、漫画のようにビクッと飛び上がってびっくりしてしまうこともありました。些細な事ですが、それだけでもドッと疲れてしまうんです。
いろんな音を聞いて状況判断をしながら、加えて頭の中では「次はあれしなきゃ、終わったらこれしなきゃ」と常にフル回転。多くの刺激を受けながら、頭が休む暇がなく、ますます疲れやすくなってしまっていました。
院内の人間関係が気になってしまう
「他人の顔色を窺いやすい」という特徴もあるHSP。それは患者さんだけでなく、院長先生や先輩などに対しても同じです。
「先輩や先生がピリピリしているけど、私のせいかな…?」
「同僚の人が怒られてる!私まで怒られている気がしてきた…」
院内の空気感に敏感で、雰囲気が悪いと、その影響を強く受けてしまいがちです。職場の人の機嫌が悪いとその感情を強く受け取ってしまい、「私のせいかも…私がなんとかしないと…」と、実際は自分のせいではなかったとしても、他人の機嫌が気になって、自分を責めてしまうことも。
HSPの人は「人に嫌われたくない」という気持ちが強い傾向があります。嫌われたくないがために相手を優先してしまい、自分の思っていることを言えない“他人軸”になりやすいのです。ですが、そうやって他人に合わせ続けていると、メンタルも辛くなってきてしまいます。
院長先生や先輩との関係がうまくいかない…という人は、自分のメンタルを守るためにも、自分に合った働き方とは何か、もう一度考えてみてもいいのかもしれません。
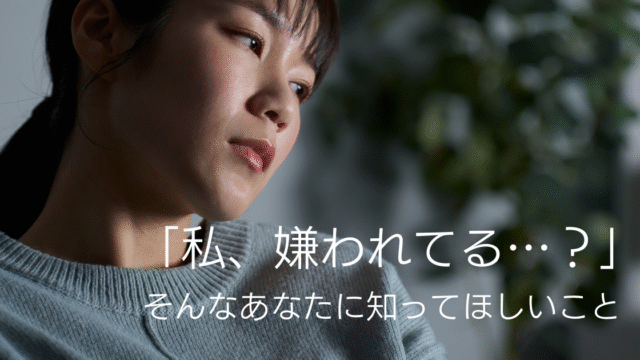
HSPの歯科衛生士が働きやすい環境とは?
他の人と同じように働けるHSPの人もいますが、筆者と同じように疲れてしまったり、つらいと感じている人も多いでしょう。HSPの歯科衛生士にとって働きやすい環境を作るためにできることを考えてみました。
周りからの刺激が少ない医院を選ぶ
刺激が多いことで疲れやすい、HSP。ずっと大きな音に晒される歯科医院という職場は、それだけでストレスになり得ます。耳からの刺激を少しでも減らすために、なるべく静かな環境で働けると良いですよね。
たとえば、私が以前勤めていたところもそうだったのですが、歯科衛生士が使える個室を完備している医院だと、他の雑音が入らないのでかなりストレスは軽減されると思います。個室までは難しくても、ユニット同士の間隔が広いだけでもマシになりますし、チェアごとに半個室のようになっている医院なら、探せば結構たくさんあります。
職場を探す時は、そういったところもチェックして、自分が働きやすい環境の医院を探してみてくださいね。
院長や他のスタッフに相談する
「職場を変えるのはちょっと…今の職場のままで、何か対策できないかな?」という人は、院長や先輩に自分がHSPであることを話してみるのも手です。騒音や情報過多で気が散ってしまうなど、自分にとって何が辛くなっているのかを分析し、相談してみましょう。
特性を理解してもらえたら、自分が楽になる環境を提案してみるのも良いと思います。たとえば、休憩をこまめに貰う、他のチェアと少し離れた場所でスケーリングをさせてもらうなど、他の人の協力を得ることで、自分にとって働きやすい環境を整えられるかもしれません。
話すのはとても勇気がいることではありますが、今の職場が気に入っているのであれば、話してみる価値はあると思います!
臨床以外の働き方も!
臨床で働くイメージの強い歯科衛生士。ですが、臨床以外でも働けるのはご存知でしょうか?臨床以外というと、行政や歯科用品メーカーでの勤務などもありますが、近年注目されているのは、フリーランスの歯科衛生士です。
- 助っ人(スポット)
- セミナー講師
- 歯科医院のコンサルティング
- 歯科衛生士の教育講師
- 採用支援
- SNS運用代行
- サロン開業
- 歯科関連のライター
「フリーランス歯科衛生士」と聞くと、経験豊富で、社交的で、人の前に立つような人物像をイメージしませんか?もちろん、そういう方もいるんですが、実はそれだけじゃないんです。私のようにHSPで人と接するのがあまり得意ではないタイプにも、フリーランスはとてもおすすめなんです。
フリーランスであれば、自分に合った環境を自分で選んで、働くことができます。
私は元よりパソコンで文章を打ったり考えたりすることが好きだったため、歯科関連のライターの仕事をさせていただいています。今では、外部刺激が少なく自分のペースで働ける環境で、在宅の歯科衛生士として働くことができています。
そう、在宅でも、歯科衛生士として働くことができるんです!在宅なら自分のペースで無理なく働くことができるので、私にぴったりの働き方でした。
フリーランスなら、自分に合った、自分がやりたい働き方で、幅広く活動していくことができます。今の職場で働きづらさを感じているのなら、選択肢のひとつとしてぜひ知っておいてほしいと思います。
フリーランス歯科衛生士についてより詳しく知りたい方はこちら↓

歯科衛生士の在宅ワークについてはこちら↓

自分にあった環境で働こう
生きづらいと言われることが多いHSP。ですが、自分に合った環境でなら、その能力を大いに発揮する事が出来る、と私は思っています。
私は、歯科衛生士という職が好きで、歯科衛生士としての誇りもありました。ですが、臨床が自分に合っていないと思った時点で、歯科衛生士という職そのものを諦めてしまいました。歯科衛生士は臨床で働くもの、という意識が強かったからです。行政などもありますが、それは狭き門で、自分には到底無理だと思っていました。
一度は歯科衛生士を離れてしまったけれど、その後D.HITと出会い、「臨床以外でも歯科衛生士として働ける」ということを知ることができました。
臨床は私に合っていないから。辛いから。できないから。
そう思って、歯科衛生士として働くこと自体を諦めていた筆者も、フリーランスになることで、歯科衛生士としてもう一度働けるようになったのです。歯科衛生士を諦めなくてよくなったのです。
もし、筆者と同じように、歯科衛生士は好きだけど、臨床が苦手で、辛くなっている方がいるのであれば、歯科衛生士の働き方は臨床だけではない、ということを知っておいてほしいと思います。
HSPの生きづらさを取り除き、能力を発揮するには、職場の人達の協力が必要な場合もあります。自分の内面のことですから、なかなか言い出せないこともあるかもしれません。新しいことを始めるのも、最初は勇気がいると思います。
でも、このまま何もせずに生きづらさを抱えているのはもったいないです!諦める前に、まずは行動してみてください。行動すれば、自分も周りの環境も変えることができます。自分が働きやすい・自分に合った環境を作ったり見つけたりすることで、HSPでも安心して心地よく働くことができます。
あなたも、自分に合った環境を見つけて、歯科衛生士として、自分らしく働いていきませんか?
HSPだからこそ、自分に合った環境を見つけることが大切です。臨床、フリーランス、在宅ワーク…働き方はいろいろあります。もし「生きづらさを感じている」ならば、D.HITの「キャリココ」を活用してほしいです!まずは、無料相談であなたの現状を聞いてもらってくださいね♪








