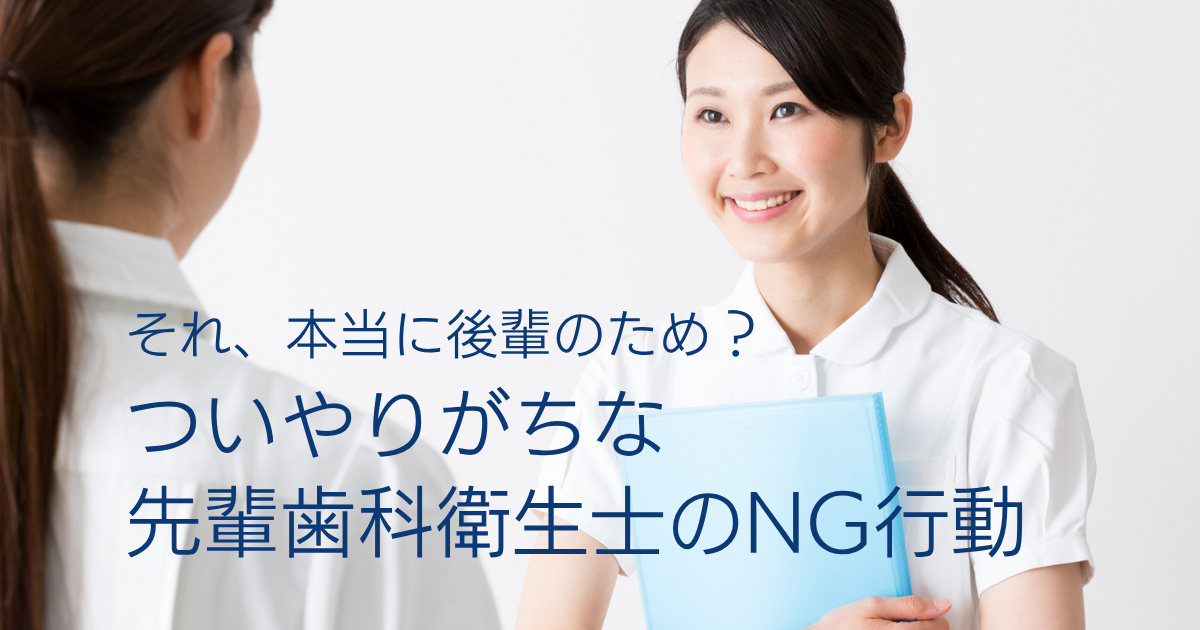「後輩ができたけど、どうしたらいい?どう接したらいい?」と戸惑っている、先輩歯科衛生士さん。
- 厳しくすると嫌われそう
- 優しすぎると甘やかしになる?
- 自分の時代とは価値観が違いすぎる…
こんな葛藤を抱えながら、日々の接し方を模索している人も多いのではないでしょうか。
先輩として後輩に接することは、ただ仕事を教えるということ以上に、その人の成長や職場の雰囲気に大きく関わってきます。どこまで任せるか、どんな風に声をかけるか、どこまでサポートすべきか…そのバランスは簡単なようで、とても難しいものです。
この記事では、「こんな先輩は嫌だ!」と思われがちなNG例をあげながら、後輩に信頼される先輩になるために気をつけることを、現場目線でわかりやすく解説します!どう接すればいいかわからない先輩歯科衛生士のみなさんに、ご自身のセルフチェックとしても活用してもらえる内容となっています。ぜひ最後までお付き合いください。
こんな先輩は嫌だ!
「職場ではうまくやっていきたい」誰しもそう思っていると思います。
歯科クリニックの「先輩・後輩」の関係性は、非常に複雑です。なぜなら歯科クリニックの歯科衛生士は、ほとんどの方が転職を経験しているから。年齢や職歴だけでは先輩・後輩と言い切れない、見えない壁があるのです。
このような複雑な関係性の中で、無意識のうちに後輩から距離を置かれるような接し方をしてしまっているケースもあります。ここでは、「なんか嫌だなぁ」「正直ちょっと苦手かも…」と思われがちな先輩の特徴をご紹介します。
感情的な指導
人間誰しもイライラすることはありますが、イライラを指導にぶつけてしまうと、後輩は萎縮してしまいます。
たとえば後輩がミスをした時、「え〜また?!」「なんでこんなこともできないの?」「余計なことしないで!」と怒りをぶつけていませんか?私も先輩を怒らせて、問診で使っているクリップボードを叩きつけられたことが何度もありました…。怒った末に、無視されたこともあります。
怒ることも、無視することも、感情にとらわれて自分をコントロールできていない状態。指導のために厳しく叱ることも時には必要ですが、そのような感情的な指導の仕方では、その内容が正しかったとしても、感情の圧に気を取られ指導内容がまったく伝わりません。
叱るときこそ冷静に。落ち着いて言葉を選びましょう。
「◯◯が難しかったかな?一緒に確認してみよう」と、気持ちを受け止めつつ前向きな言葉を選ぶことで、伝えたいことがちゃんと伝わります。
過干渉・過保護
後輩にあらゆる作業を細かく指示したり、先回りしてサポートしていませんか?
過干渉や過保護な先輩は、現場でとてもよく見かけますが、本人はそれが「過干渉・過保護」である自覚がないことがほとんどです。ではなぜそうなってしまうかというと、「失敗させて落ち込ませたくない」と思うから。後輩の失敗を未然に防ごうとするあまり、失敗する前に手助けをしてしまっているのです。比較的、責任感の強いチーフ歯科衛生士にありがちな行動と言えるでしょう。
たとえば、診療補助で根治の準備の際、いつも「〇〇は持ってきておいたよ」と言って手伝ってくれる先輩。手が空いていたらお互いに助け合うことが必要な場面ももちろんありますが、もしかしたら後輩は「最初から最後まで、自分でやりたかったな…」と感じているかも。
これでは後輩の「自分で考えて動く力」が育ちません。「よかれ」と思ってやっていることでも、それは後輩の成長の機会を奪っているという考え方もできます。
一旦任せて、見守ってみましょう。最初から全部説明するのではなく、「まずはここまでやってみて。わからなかったら聞いてね」と段階的に任せることが自立につながります。“任せて見守る”スタンスをとることで、相手は「信頼してもらえている」と感じます。先回りのサポートではなく、成長を信じて任せる勇気も大切です。
曖昧な指示をする
私が個人的に一番やめてもらいたいと思うのは、これです。
「適当にやっておいて」「なんでもいいよ」という曖昧な指示は、後輩をとても混乱させてしまいます。これは一見、後輩を信じて任せているようでもありますが…「なんでもいい」と言いながら、実はなんでも良くない、という場合がほとんど。後輩は、何が正解か、どうしたらいいかわからず不安になり、結果的に自信をなくしてしまうこともあるでしょう。
特に、歯科の臨床において「誰が、どの程度までやればいいのか」ということが曖昧だと、とても困ります。たとえば、技工物の依頼。誰が指示書を記載し、誰が発送するかなどは、歯科クリニックによって異なることなので、やる必要があるのかどうかは最初に指示してほしいです。
先輩歯科衛生士の中には「普通に、歯科クリニックではここまでが歯科衛生士の仕事でしょ」というのがあったとしても、それは思い込み。新人歯科衛生士にはその当たり前がわからず、困惑する原因になってしまうのです。
指示は具体的に。「〇〇は、〇〇まで歯科衛生士がやって、そのあと〇〇は受付さんがやってくれるよ」と流れを意識して伝えると理解が深まります。
他の人と比較する
誰でも、他人と比較されると嫌ですよね。「◯◯さんはもっとできてたけどね」と貶すのはもちろんNGですが、特に気をつけたいのは、「褒める時でも」他の人と比べないこと。
- 「◯◯さんより仕事が早いね!」
- 「新人さんの中で1番上手にできてるよ!」
- 「◯◯さんに比べて、よく気がついてくれて助かるよ」
こんなふうに、他人との比較で褒める人は意外と多いです。
褒める時・叱る時に関わらず、「他人と比べる」行為はプレッシャーになります。過度なプレッシャーは、仕事をする上で百害あって一利なし。前向きに褒めているつもりでも、職場内での関係性が悪化して逆効果になってしまうかもしれません。
褒める時は、他人との比較ではなく「感謝の気持ち」で伝えましょう。比べるなら、他の人ではなく、過去の後輩自身と比べて、その「成長」を軸にすること。「前よりスムーズだったね!」「上手になったね!」という声のかけ方が効果的です。
自分の価値観を押し付ける
「私の時はこうだったよ」「普通はこうするでしょ」「常識的に考えて…」と、自分のやり方や常識を基準にして話すのはやめましょう。時代や環境が違えば、常識や考え方も当然違ってきますし、先輩の「当たり前」は後輩の「当たり前」ではないのです。
たとえば、カンファレンスの際に、担当患者さんの歯周治療の方向性について後輩に意見を求められ、「“普通”だったら先にSRPするからそれでいいんじゃない?」なんて言っていませんか?この「普通」という言い方、先輩がそれをなぜ「普通」と思うのか後輩にはわかりませんし、価値観の押し付けだと感じてしまうかも。この場合は「ブラッシング指導を先にしてしまうと歯肉が引き締まって、SRPしにくいから、先にSRPをした方がいいんじゃないかな?」というふうに理由も一緒に伝えると、後輩も受け入れやすく、成長にもつながります。
自分の考えを伝える時は、しっかり理由も添えて。さらに、「◯◯さんはどう思う?」と問いかけ、押しつけることなく相手の意見に耳を傾けられるとベター。自分の考えを伝えつつ、相手の考えも尊重することで、相互理解を深め、信頼を育てます。
人によって言ってることが違う
これは私が実際に経験して嫌だったことなんですが、先輩によってやり方が違うと、後輩は困ります。
たとえば、A先輩に「これは洗浄液につけて滅菌すればOK」と言われてそうしていたら、B先輩から「これは水洗いしてからじゃないと洗浄液につけちゃだめだよ!」と怒られてしまったことがありました。
歯科の現場ではよくあることかもしれませんが、「結局どうすればいいの?」と後輩が混乱してしまう原因になります。
院内のルールや方針は、スタッフ間で統一しましょう。指導内容に一貫性を持たせることで、安心して学べる環境が整います。後輩に伝える際は「こういう理由で、このやり方で統一してるよ」と背景も一緒に説明をしましょう。
愚痴などを後輩の前で言う
- 「あの患者さん、めんどくさかったよね…」
- 「先生、ほんと気分屋で疲れるんだよね…」
そんな会話を、後輩の前でしていませんか?ネガティブな発言は、職場の雰囲気を重くして、後輩のモチベーションを大きく下げてしまいます。
スタッフ同士の陰口・悪口は言うまでもありませんが、特に注意すべきは、院長への愚痴だと思います。共感を得て仲良くなろうと意識的に愚痴を言う先輩もいますし、「共通の敵」を持つことで結束力が強まることは珍しくありませんが、それは結果的に「ここで働いて大丈夫かな…」と不安になってしまう要因にもなります。
後輩は先輩の姿勢を見て、職場を評価しています。愚痴の前に、まずは感謝の気持ちを持ちましょう。陰で愚痴を言うだけでその本人に直接意見を言えないのは、自信のなさの表れでもあります。もし院長に対して不満があるのなら、改善してほしいこととして直接伝えたほうが良いでしょう。そんなあなたの姿を、後輩はしっかり見てくれています。
忙しいオーラで近寄りがたい
歯科医院において、かなりの確率で多いのがこのパターンです。
- いつもバタバタしている
- 笑顔がなく目つきが怖い
- 声をかけてもピリピリしている
- 話しかけないでというオーラがでている
先輩がこんな雰囲気だと、後輩は質問や相談があったとしてもためらってしまいます。常に忙しそうだと声をかけることを躊躇してしまい、小さな疑問や不安が解消されないままで、結果的にミスやトラブルにつながってしまいます。
私がコンサルを担当したある歯科クリニックで、入職して1ヶ月ほどの新人歯科衛生士さんの指導を任された時のことです。まずは見学に行かせていただいたのですが…滅菌あがりの器具を持って院内をうろうろしている新人さん。外科用器具をどこにしまえばいいのかわからず、1分くらい、いろんな扉を開けて、歯科クリニックの中を探し回っていました。その時、先輩歯科衛生士は5名いたのですが、みんな自分の仕事に追われ、誰も話しかけようとしませんでした。
みんなが自分のことで忙しく、新人教育にまで意識を向けられない…だからこそ私が指導担当として呼ばれたのですが、誰も新人歯科衛生士と目を合わせようともしない、質問したくてもできないような雰囲気には、正直驚きました。これでは新人さんも、聞きたくても聞けない状況となってしまい、小さな疑問を解消することができませんよね。
こうした日々の小さな疑問や不安が放置され、大きなトラブルにつながったら、結局、やることも負担も増えてしまいます。先輩としても、結果的に損失となる可能性が高いのではないでしょうか。疑問は小さいうちに解消しておきたいものです。
忙しくても、目を合わせて「ごめん、あとで話そうね」とひと言添えるだけで、後輩は安心します。質問しやすい空気づくりを意識しましょう。
「できて当然」な態度
誰でも「認めてもらえること」が頑張るモチベーションになりますよね。「できて当たり前」な態度や、「こんなことで満足しているの?」という態度は、後輩のやる気をしぼませてしまいます。
あなたにとっては簡単なことでも、後輩にとっては大きなチャレンジかもしれません。自分が新人だった頃のことを思い出してみましょう。
できたことに対して「よく頑張ったね」「さっきの処置、前よりスムーズだったよ」と、小さな成長にもしっかり言葉をかけましょう。認める言葉をかけるだけで、モチベーションの源になり、後輩は自信を持って次に進めるようになります。
自立を促そう!後輩指導のポイント
後輩から見た「こんな先輩は嫌だ!」と思われがちなNG例をあげてきましたが、どうでしょうか。悪気なくやってしまっていることもあったのではないでしょうか?
後輩の自立を促す指導には、いくつかポイントがあります。
- 信じて見守る姿勢
- 否定せず「認める」伝え方
- 努力や行動を見て評価する
忙しい現場、先輩としては、つい先回りして説明したくなる場面が多くあるでしょう。新人が初めてクリーニングの準備をしているとき、ちゃんと準備ができるかな…と心配になりますよね。でもここは、グッとこらえましょう。ポイント1つ目は信じて見守る姿勢です。「見守る」と言っても、ずっと横で「見張る」のとは違います。「もしわからなかったら、いつでも聞いてね」と声をかけ、あとは任せて口を出しすぎず、信じて待つ。まずは自分の力でやってみて、間違った部分があれば、あとで一緒に振り返りをすればいいのです。こうした経験が、後輩の「自分でチャレンジしてみる力」を育てます。
後輩に何かを伝えるなら、ポジティブな声かけを意識しましょう。ポイント2つ目は、否定せず「認める」伝え方です。伝え方への配慮は、その後輩が今後成長できるかどうかを大きく左右します。たとえば、後輩が印象を採るときに、一生懸命やったけれど口腔内に挿入する前に印象材が固まってしまったら…どう声をかけるのが良いでしょうか?「また固まっちゃったの?」「なんでこんなこともできないの?」というのは「否定」になり、後輩は自信をなくしてしまいますよね。大事なのは、頭ごなしに否定せず「ここまでしっかり手順を覚えてたね!あとはタイミングだね!」とまずは努力のプロセスを認めること。そして、「次はこんなふうにするといいかもよ」と前向きなアドバイスに変えて伝えることで、後輩も「次はこうしてみよう」と素直に吸収してくれるようになります。「ここをこうするともっと良くなると思うよ」と、改善点を具体的かつ前向きに伝えることを意識しましょう。
そして最後に3つ目のポイントは、努力や行動をしっかり見て言葉で評価することです。どんなところを見ればいいかというと、たとえば…
- いつもより早めに出勤してチェアの準備をしてくれていた
- 患者さんへの声かけのトーンが柔らかくなった
- 先輩の動きを見て自分から器具を準備していた
一見どれも些細な変化だと思いがちです。こうした変化は、見逃されやすいものです。しかし、ここに気づき、言葉にして伝えることで「自分の行動には意味がある」「ちゃんと成長している」と後輩は実感できます。評価されない環境では、いずれ後輩は動かなくなってしまいます。どんなに小さなことでも、「見てくれている」と感じられるだけで、後輩のモチベーションは大きく変わってくるんです。
- 「さっきの準備、スムーズだったね」
- 「よく気づいてくれたね」
- 「この前より落ち着いて説明できてたよ!」
大切なのは、結果だけでなく、その“過程”を評価すること。歯科クリニックの現場は忙しく、つい結果主義に偏りがちですが、後輩の「努力している姿」や「チャレンジしている姿勢」を先輩が見てくれているという実感が、信頼を育みます。見て、認めて、伝える先輩がいる職場では、後輩の笑顔が増え、自発的な行動が生まれていきます。
後輩指導で大切なのは、「正しさ」や「技術の多さ」ではありません。人として「信頼される存在」であることです。
忙しい現場の中で、つい口を出したくなったり、効率を優先して後輩の失敗を防ぎたくなったりすることもあるでしょう。でも、後輩はその姿をよく見ています。「この先輩は、自分を信じて任せてくれている」「ちゃんと見て、認めてくれている」と感じたときにこそ、後輩は大きく成長していきます。
「ここまでできたね」「次はこうしてみよう」と、前向きな声かけを忘れずに。そして小さな努力も見逃さず、しっかりと伝えてあげましょう。そんな日々の積み重ねが、やがて後輩から「この人と働けてよかった」と思ってもらえる信頼関係を築いていきます。今日から少しずつ、そんな先輩像を意識してみましょう!
後輩指導の経験は、とても価値があります。この人材育成のスキルを磨けば、さらにスキルアップができますし、人材育成コンサルタントなど新しい働き方も見えてきます。もし、新たに挑戦したいと考えているなら、D.HITのキャリココで詳しい話を聞いてみませんか?
D.HIT公式LINEを登録すると無料相談を予約できますので、試してみてくださいね!